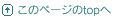日本における外科医療の将来と周術期感染管理
日本外科感染症学会
前理事長 草地信也
(東邦大学名誉教授、東邦鎌谷病院外科)
外科医療の今後
外科医を取り巻く医療環境は今後大きく変化する可能性があります。国は急性期病院と慢性期病院の在り方を明確に区別する方針を打ち出しており、急性期病院には重症度、医療・看護必要度の高い患者さんの割合を高くして、早期退院をはかり、病床数の減少を求めています。さらに働き方改革で医療従事者の労働管理を打ち出しています。
このため、病院経営の面から考えると、急性期病院は重症度、医療・看護必要度の高い手術患者の割合を高くする必要があり、手術症例を稼ぐ外科医は貴重な存在となります。
また、術後患者は早期に退院させ、術後合併症を起こした患者でもなるべき早く後方支援病院へ転送させることが必要となります。さらに、周術期管理から外科医の負担を減少させ、外科医は手術に専念できる環境を作る必要があります。その目的で日本外科感染症学会では、現在日本の外科医が行っている日本の周術期管理をマニュアル化し、多くの職種の方に周術期管理に協力していただけるようなマニュアルを作成しています。
術後入院期間の短縮
手術患者の早期退院を達成するためには、合併症そのものの頻度を減少させること、合併症を発症した患者は早く確実に治療すること、また、早く後方支援病院へ転院するためには、MRSAやC.difficile、MDRPなどの耐性菌を保菌させないことが重要となります。
そのためには、まず、手術部位感染(SSI;Surgical Site Infections:手術操作が及ぶ部位に発症する感染症=切開創SSI、臓器/体腔感染SSI)だけではなく遠隔感染(RI; Remote Infection: 手術操作が及ばない部位の感染症=呼吸器感染症、血管内留置カテーテル関連敗血症、尿路感染症、抗菌薬関連性腸炎)も含めたすべての周術期感染症のサーベイランスを行い、その予防策・対応策を徹底させる必要があります。
そして、急性期病院の病床数減少のためには周術期感染症を早く、確実に、きれいに治療することが求められます。早く、確実にとは、例えばMRSA菌血症にはバンコマイシンを使わずに最新の抗MRSA薬(DAPまたはLZD)を使うことです。きれいに、とはMRSAやその他の耐性菌、C.difficileを保菌しないようにして後方支援病院への転院を容易にすることです。そのためには、単に安い薬剤を推奨したり、MRSAやC.difficileが多い欧米の抗菌薬ガイドラインに従うのではなく、新しい対応を考えなければなりません。日本では、もともとMRSAもC.difficileも少なかったのですから、今までの日本の周術期管理に大きなヒントがあると思います。この件は本学会が作成中の周術期管理マニュアルに反映させたいと考えています。
一方で、働き方改革によって外科医の労働時間を短縮する必要があり、外科医の負担軽減は急務であると考えます。手術は外科医が行わなければなりませんが、ある程度の周術期管理は将来的に集中治療科や感染症科、感染制御部、感染管理薬剤師、放射線科医、消化器内科医、ICN、Nurse practitionerに協力していただく必要があると考えます。そのことが、外科志望の医師を増やし、日本の外科医療のレベルをさらに発展させることと考えます。しかし、現状では外科の周術期管理の経験をお持ちの感染症科医は少なく、欧米のエビデンスやガイドラインに頼らざるを得ません。残念ながら欧米並みの管理を行うと手術関連死亡率の増加や耐性菌感染の増加が危惧されます。事実、従来日本ではほとんど発症していなかったC.difficile腸炎が急増した背景には欧米並みの抗菌薬の使用方法が“適正”とされたためではないかと考えます。そこで、日本外科感染症学会では、従来日本の外科医を中心として行ってきた日本の高いレベルの周術期感染の管理・治療を学会として指導する必要があると思い、周術期感染管理のマニュアルを作成します。
日本の周術期管理
“外科医を中心として行ってきた日本の高いレベルの周術期感染の管理・治療”と強調した理由は、日本の周術期感染対策・管理が一部の感染症科や感染制御部、また、一部の集中治療科の先生方に正しくご理解いただいていない現実があるためです。外科の経験がなくて外科医療の現状をご存じない感染症科医や一部の集中治療医、感染制御部のスタッフから“日本の外科医はエビデンスがない経験的な医療ばかりやっている”、“ドレーンを入れすぎる”、“経鼻胃管の留置が多い”、“抗菌薬の使用が適正でない”などのご指摘を受けています。
外科以外の診療科の先生方や様々な職種の方に日本と欧米の手術そのものの違いや、欧米に比べて手術関連死亡率が1/10~1/5であり、その理由として日本の外科医は最後まであきらめずに治療してきたこと、また、国の保険制度がそれを許容したこと、すなわち欧米のようなエビデンスがある治療だけでは不十分であることを説明するのは非常に忍耐と労力を要することです。ただでさえ忙しい外科医にとって大きな負担と精神的な苦痛になっていることもあるかと考えます。また、外科志望の初期研修医に誤った外科医の印象を与えて外科医への道を諦める一因になることもあろうかと思います。
これらの点について、さらに解説いたします。
術後腹腔内感染の患者さんの治療を考えるうえでドレーンの必要性について言及すれば、ドレーンの有無の問題は、患者の状態、病変の進行度、術者の技術、併存疾患とともに、その施設の周術期管理の体制によっても大きく異なります。
例えば、外科医が朝から夜まで次々と手術をやっている間にでも、放射線科医が術後腹腔内膿瘍を発症した患者さんにIVRでドレナージしてくれる体制ができている施設や、外科医が多く、手術室も麻酔科医もスタッフが揃っていて、いつでも再手術を行えるような施設ではドレーン留置は必要ないかもしれません。また、欧米のように術後合併症で日本の数倍の患者さんが亡くなっても“やむなし”とするならばドレーンも不要です。しかし、日本では外科医が自らIVRを行う施設も多く、また外科医が少なくてスタッフも十分でない施設の方が圧倒的だと思います。また、外科医の過労が危惧される施設も多いことと考えます。そのような施設でも日本の平均的な術後管理成績・能力が要求されます。ドレーンが留置してあればそこからガイドワイヤーを入れることによって、外科医でも多臓器損傷の危険性を低めて比較的安全に容易にIVRによるドレナージができるかもしれません。一概にドレーンが不要とは言い切れないと考えます。このようなことは外科医であればだれでも理解できることではありますが、外科の経験がないにもかかわらず治療に参加することを強いられる感染症科医や感染制御部の薬剤師やICNにとっては欧米のガイドラインやエビデンスを根拠に治療するしか道がないことはやむを得ないことです。外科医がこの点をご理解して頂くように説明するのは大変な労力を要しますし、大きなストレスでもあります。
この件も本学会が作成中の周術期管理マニュアルに反映させたいと考えています。
また、術後にTPN管理中の患者に発症したMRSAによる血管内カテーテル関連性菌血症に対してバンコマイシンを投与される感染症科医や感染制御部、感染管理薬剤師も未だに多いと思います。このような患者さんは何らかの合併症があってTPNを行っているのですから、このような患者さんの菌血症は確実に治さないと、どんどん悪循環に陥ってしまいます。不幸な結果になった場合の患者家族への対応や、裁判になった場合の資料の作成などは外科医が行うわけですから、ここは最新の抗MRSA薬で確実に治療していただきたいと思います。最新の抗MRSA薬のエビデンスは未だ十分とは言えませんが、最新の抗MRSA薬の後発品が発売された欧米では投与機会が大幅に増えており、治癒率が高まり、病院関連型のMRSAは確実に減っています。最新の抗MRSA薬は日本のガイドラインでも推奨されていますし、最新の米国の心内膜炎のガイドラインにおいても推奨されています。いずれバンコマイシンは使われなくなると思いますので、今から最新の抗MRSA薬を使って頂きたいと思います。MRSA=バンコマイシンとしか発想できない感染症科医、感染管理薬剤師に最新の抗MRSA薬が不適正使用と言われては、患者さんにとっても外科医にとっても大きな問題と言わざるを得ません。何よりも、新しい治療薬が市販されたら、ます、専門家である感染症専門医が使ってその経験を公にしていただかなければ一般の医師は使えません。この件も本学会が作成中の周術期管理マニュアルに反映させたいと考えています。
また、“MRSA腸炎はない”とされており、この疾患を口にするだけで非難されることもありました。しかし、実際、現在でも極わずかですがMRSA腸炎は存在し、死亡例もあります。このような症例の多くは裁判になるので論文発表は難しいですが、MRSA腸炎は医療裁判の場で確実に存在します。問題は、MRSA腸炎は診断、病態が確立されておらずガイドラインにも記載がないために裁判でも医療側の責任が問われず、現在でも不幸な結果が繰り返されているということです。外科医や感染症科医がMRSA腸炎を早期発見し、治療しないで、だれが治療するのでしょうか?これでは本学会や感染症科の存在意義が問われることではないでしょうか?日本外科感染症学会ではMRSA腸炎検証プロジェクトチームを組織し、裁判症例、和解症例を検討し、だれが見てもMRSA腸炎だ!という症例をまとめてMRSA腸炎の存在を検証したいと思います。
さらに、CHDFやエンドトキシン吸着療法(以下PMX)を否定する集中治療医も多いです。
エビデンスがないというのがその理由と考えます。しかし、例えばPMXの海外の比較試験では外科的処置によって敗血症が治癒できない腹腔内感染の症例が対象となっています。つまりsource controlが不成功の状況でPMXの有効性を比較しています。Source controlができなければ最後には死亡しますので、差が出るわけはありません。しかし、短期的な予後はPMX群が優れ、施行後数日間は循環動態が安定することは確かめられています。この間にsource controlに成功すれば患者は救命できる可能性が出てきます。つまり、日本では何度でも最後までsource controlができるので、一人でも多くの周術期感染患者を救うためには一時的にでも全身状態を安定させるPMXも有用なのです。この点も日本と欧米の大きな違いであり、このような点が手術関連死亡率の差に影響を与えていると考えます。
この件も本学会が作成中の周術期管理マニュアルに反映させたいと考えています。
一方、院内感染対策には手指衛生が重要であることは当然ですが、例えば、感染創の処置時に手指消毒のタイミングやスタッフの役割を示したマニュアルを制定している施設はまだ少ないと考えます。
本学会では今後、関連学会とも相談し感染創の標準的処置マニュアル(仮)”を作りたいと考えます。この中には、感染創の管理、ドレーンの管理、NPWT、呼吸管理中の患者の病室配置などに関する詳細なマニュアルを整備したいと考えます。
また、ICNと共同で行うべきは、サーベイランスです。手術部位感染対策は1999年のCDCガイドライン公表から盛んにおこなわれてきました。しかし、欧米では、遠隔感染は各々独立した感染対策が行われており、日本のように術後呼吸器感染対策として、そのもっとも大きな原因ともいえる呼吸不全の予防のために周術期の輸液を検討するようなことは行われていません。日本では遠隔感染もまた外科医が治療しており、予後や入院期間、医療費に重大な影響を与えるため、サーベイランスや対策マニュアルやガイドラインが必要となります。よって、本学会はあくまでも外科医目線の、外科医のための感染対策を主導すべきで、そのためには遠隔感染のサーベイランスも整備すべきと考えます。将来的には、本学会教育施設には遠隔感染も含めたサーベイランスを認定条件とすべきと考えます。感染症例を蓄積することによって各施設の研究も容易になりますし、学会主導の多施設共同臨床研究も容易になると思います。処置マニュアルと遠隔感染を含めたサーベイランスは後述の日本の特殊性、先進性を示す重要な要件で、ICNとの協調が不可欠です。これらの件は関連学会と協調してICNとともにサーベイランスを設置したいと考えます。
海外の学会との協調
海外の外科感染症学会とのコラボは従来から本学会が取り組んできたことで、今後も継続したいと考えています。ただし、日本の周術期管理は現在でも世界最高レベルにあると考えます。そもそも、日本でしか行われていない難易度の高い手術もあり、その管理技術は世界唯一のものです。日本は周術期感染による死亡率や耐性菌の出現率でも世界的にも極めて良好な成績を収めています。海外の学会に対し、例えエビデンスはなくても、単に日本のサーベイランス結果、成績、管理体制をそのまま公表することで多くの海外からの参加者を集めることができると考えます。日本では、未だ明確なエビデンスに乏しい治療も承認されている場合もあり、このため他国の追随を許さない成績を収めていることが海外の研究者にご理解いただければ、自ずと注目を集めると考えます。よって、海外の外科感染症学会とのコラボを考えると、日本の特殊性を前面に出した演題を公表することが重要であると考えます。日本より成績が悪い諸外国のやり方に合わせる必要はなく、日本の外科医療を勉強していただく場を提供することが、彼らのニーズに合ったことだと思います。海外からの参加者には、日本では明確なエビデンスがない治療もできるので成績が良いことを学んでいただきたいと思います。
薬剤耐性菌対策
抗菌薬の適正使用は学会として取り組んでいきたい最も大きな問題だと考えます。世界的に薬剤耐性(AMR; Antimicrobial Resistance)対策が提唱されています。日本でもAMRは盛んに取り上げられ、抗菌薬の適正使用が話題になっています。しかし、日本のAMR対策は、10年ほど前の欧米のエビデンスに基づいた欧米のガイドラインに準じた抗菌薬使用方法を推奨しています。いわば現在、欧米で院内感染として最も多いといわれているC.difficile腸炎や様々な耐性菌を発生させた抗菌薬療法を推奨しています。振り返れば、日本では2005年ごろまではC.difficile腸炎はほとんど発症していませんでしたが、欧米の抗菌薬療法を取り入れ、PK-PD理論に基づいた高容量投与が行われだしてからC.difficile腸炎が発症したと考えられます。ちょうどこの時期はTAZ/PIPCが2.5g製剤(TAZ 0.5g +PIPC 2.0g)から4.5g製剤(TAZ 0.5g+PIPC 4.0g)に変更された時期に一致するのではないかと考えられます。その背景には、欧米では腹腔内感染症の抗菌薬療法は、軽症・中等症でも、下部消化管に限らず、上部消化管、肝胆膵手術でも嫌気性菌や耐性菌をも目標とした抗菌薬療法が行われています。これは最新のSISの腹腔内感染症のガイドラインにおいても同様です。日本以外の国では、前述のように治療機会が限られ、日本のように最後まで治療できないので、すべての分離菌、しかもMICが高い菌も想定して抗菌薬療法を行わなければなりません。日本でも重症例にはその通りでよろしいかと思いますが、中等症・軽症の患者さんには治療のチャンスが何度もありますので、初期からすべての分離菌、耐性菌までも視野に置いた抗菌薬療法を行うことは無用な耐性菌の出現機会を増加させていると考えます。すなわち、中等症、軽症では分離菌の中で原因菌に対する抗菌薬療法で十分であり、このことが耐性菌の出現を予防する最も効果的な方法であると考えます。
腹腔内感染症の抗菌薬療法については、軽症・中等症に対する抗菌薬療法を、抗嫌気性菌作用の有無で学会主導の比較試験(対象:上部消化管手術、肝胆膵手術)を行いたいと思います。ポイントは、腸内細菌叢を保ち、菌交代現象を防ぐ意味で、抗嫌気性菌作用のある薬剤、抗腸球菌作用のある薬剤、胆汁移行性の良い薬剤、抗菌薬の高用量投与の適応を示すことと考えます。
周術期感染管理の将来像
最後に、周術期感染管理の将来像について考えてみたいと思います。
消化器外科医、心臓外科医、脳外科医は減少の一途をたどっています。医学生に聞きますと外科医志望の学生は多いと思いますが、前期研修期間に考えが変わってしまうようです。
そのもっとも大きな要因は外科医の労働条件ではないかと考えます。術者に対するインセンティブはどこの病院でも行っていますが、若い外科医にとって最も過酷と感じるのは術後管理ではないかと思います。将来的には、術後感染症は、担当外科医の指導の下で、Nurse practitioner、放射線科医による体腔内膿瘍ドレナージ(IVR)、消化器内科による胆道ドレナージ、内視鏡下ドレナージを依頼するような体制を作り上げる必要があると考えます。現状では、外科の経験がない感染症科医、感染制御部は欧米のガイドライン以上の治療は難しいかと思いますが、本学会が主導し、現在の日本の外科医が行ってきた高いレベルの周術期感染症の治療を習熟していただければ、外科医の労働条件も改善され、外科医が増えることを期待したい。
結論として、これからの日本外科感染症学会の基本理念として、現在の高いレベルの日本の周術期感染管理を保ながらも、集中治療科、放射線科、消化器内科感染症科医や感染制御部、感染管理薬剤師、ICN、Nurse practitioner、とともに日本の周術期感染症診療の標準法を明確に打ち出し、エビデンスを構築する。現在の日本の周術期感染管理を結果として日本独自のサーベイランスデータに示せば、おのずと海外の研究者、外科医、感染症科医は本学会に集まってくることと思います。本学会は、欧米の手法にとらわれず、日本の手法のデータを示して明らかにすることだけで世界をリードすることができます。
このような方針で日本外科感染症学会を発展させていきたいと思います。機会をいただければ私が直接本学会の方針、日本外科医療、周術期感染管理について説明させていただくことも可能ですし、また、今まで日本の外科医が行っていなかった優れた予防対策や治療法があれば是非ともご指導いただきたいと思います。
皆様からのご意見をお待ちしております。